【IDC2021】『天穂のサクナヒメ』や『アンリアルライフ』のクリエイターたちが語る、知っておきたいインディー知識。パブリッシャー契約から税金周りまで
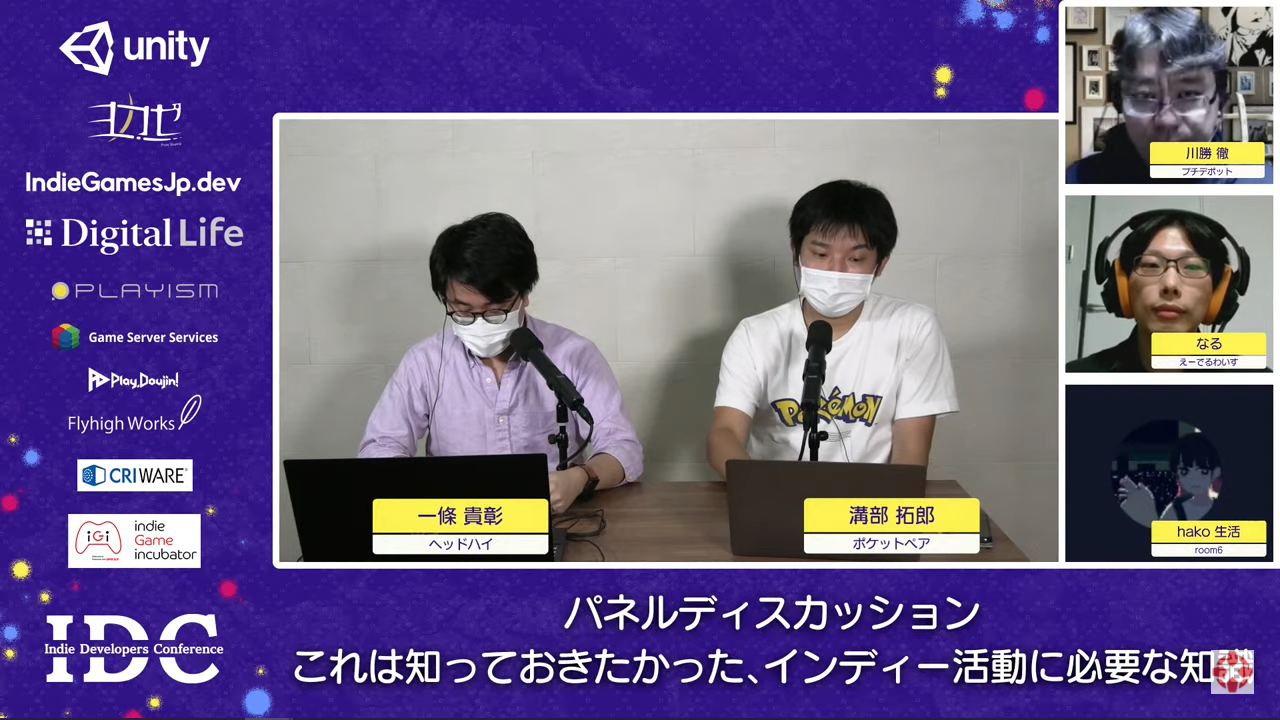
インディーゲーム開発者向けのカンファレンス・Indie Developers Conference(以下、IDC)が8月21日に開催され、カンファレンスの最後に登壇者を集めたパネルディスカッション・「これは知っておきたかった、インディー活動に必要な知識」が開催されました。
参加者は『グノーシア』を開発したプチデポットの川勝徹氏、『クラフトピア』のポケットベア代表・溝部拓郎氏に加え、『アンリアルライフ』のhako 生活氏、そして『天穂のサクナヒメ』のえーでるわいす代表・なる氏の4名。
いずれも実績を出しているクリエイターたちであり、自作を開発、リリースするにおいてさまざまな経験をしてきています。彼らからインディー開発に役立つ知識を、弊誌の代表であるヘッドハイ代表・一條貴彰氏が司会となってうかがいました。
パブリッシャーとの契約はどんなやり取りをするのか?
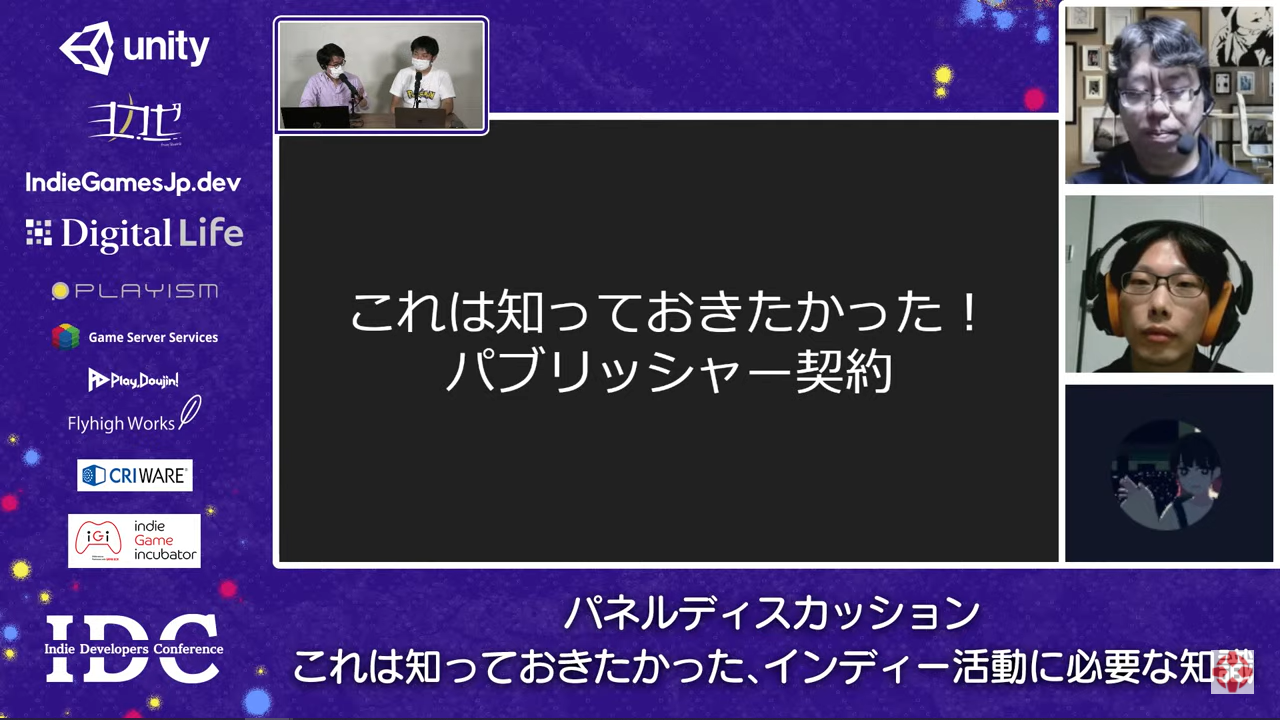
まず最初のトークテーマは「パブリッシャーとの契約で知っておきたかったこと」が挙げられました。
インディー開発において、自作を広く販売することを考えるとパブリッシャーとの契約はとても重要な要素のように思えます。しかし、参加者によってはさまざまな付き合い方があることが、ここでは語られました。
川勝氏は『メゾン・ド・魔王』でははいくつかの会社とパブリッシャー契約を結んで販売しましたが、『グノーシア』では契約を結ばず、セルフパブリッシングで進めていました。
川勝氏がパブリッシャーと契約した利点として「やはりロイヤリティーや権利周りにおいて、特に日本の会社は優しい」と紹介。一方、海外のパブリッシャーは基本的にワールドワイドの市場を狙うので厳しく、「割とタフな交渉をやらなくてはいけない」と自分の経験を振り返りました。
また川勝氏は、海外の会社との交渉する場合のコミュニケーションについても言及。交渉のやり取りをする際、言語の問題もあったゆえ、間に人を入れて行っていたとのことです。
同じ問題で、溝部氏は中国の会社とやりとりしていた経験を語りました。「原則、日本で進んでいたが、後には英語でのやりとりになった」とのこと。言語の問題に悩まされるも、「最終的に責任を持っていくのは自分」なので、ひとつひとつ契約書をチェックしていたそうです。
パブリッシャー契約を結んだ後の問題として、なる氏はパブリッシャーの宣伝活動に不足を感じるケースを紹介します。たとえば宣伝用の画像素材制作などについては、開発者が用意したほうが良いのだそうです。
なる氏は「宣材でいいものを作ろうとすると、結局自分でやったほうがいい」とのこと。自作で一番推したい部分は開発している自分がよくわかっているからであり、これがパブリッシャーに任せると意外にできないことがあるそうです。
また「パブリッシャーは宣伝をやるっていうけど、実際はあまりやってくれない」こともあるとのこと。溝部氏は「開発者は死ぬ気でPV取るために宣伝してる」スタンスのため、どうやら開発側とは宣伝の意識についてギャップがある模様です(モデレータ 一條追記:宣伝については契約時に具体的な回数・金額目標で取り決めをすると良いです)。
「思ったほど、宣伝をお任せできない」ため、パブリッシャーはいらないんじゃないか? と思うかもしれません。そこで、なる氏はパブリッシャー契約の利点として「やはり販売の雑務をお願いできることや、フォーラムのサポート、セールの対応などをやってもらえること」があると説明。やはりSteamでセールなどを行うときも、けっこうな作業が必要になるため、そこをやってもらえることは開発者のコストダウンとしても大きいとのことです。
一方、マルチプラットホームで展開する作品ならではの悩みも。なる氏は『天穂のサクナヒメ』をパッケージ販売していますが、ダウンロード販売ではなくフィジカル販売に関しては「パブリッシャーがいないとどうしようもない」と断言します。そもそものソフトの流通や製造などの雑務のほか、特典作りといったものはパブリッシャーではないと難しいとのことでした。
そんな中、hako 生活氏は「開発者自身で宣伝する部分と、パブリッシャーが雑務を担当してくれる合いの子」として、レーベルを打ちだすことによるブランディング戦略について解説。
昨年room6は「ヨカゼ」のレーベルを立ち上げています。このレーベル手法によって、自作を宣伝することに効果を上げつつ、雑務はパブリッシャー側が担当するという住みわけを行ったそうです。これもhako 生活氏が「命をかけて自分の作品をどう見せたいか」を考えた結果、編み出した手法とのことです。
知っておきたかったSteamリリース時の手続き
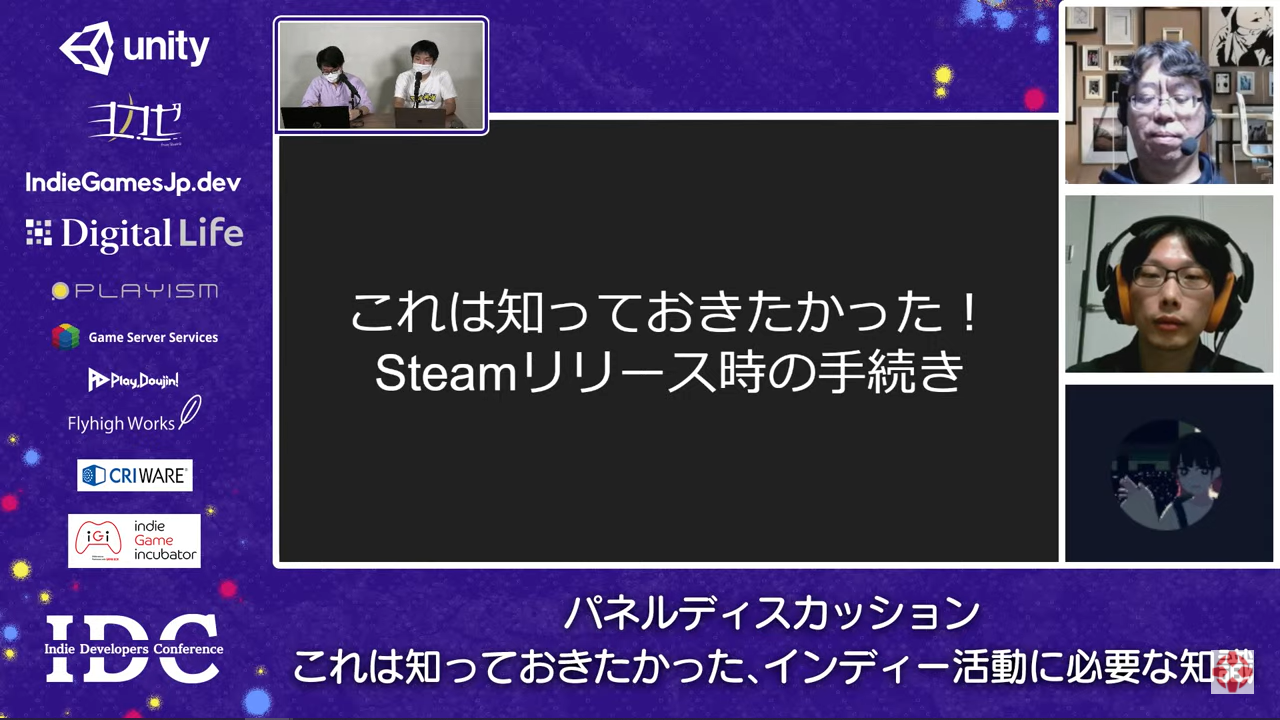
続いてSteamでゲームをリリースするときの手続きについて語られました。いまインディーゲームをリリースするプラットフォームとして、最大のものであるSteamですが、実際に作品を販売するときにはさまざまなハードルがあります。
川勝氏はこうした手続きについて「ほとんどパブリッシャーと組んでやっている」と説明。『グノーシア』はPS Vitaやswitchではセルフパブリッシングですが、SteamではPLAYISMに任せています。
パブリッシャーに任せる理由には「Steamでのリリースは、ある程度型は決まっているのでやりすやすいが、パブリッシャーに雑務をお願いしたい」というのが大きいそうです。
またパブリッシャーに任せるときも、開発のメンバーの他にもうひとり交渉のメンバーがいるといいと考えているとのこと。川勝氏は交渉も全てやっていますが、そうしたメンバーがいればセールなどの雑務を切り分けられる利点がある、と語りました。
ただ、こうした交渉ごとのメンバーが加入したとして、既存の開発メンバーと上手く行くかという問題も提起しています。「開発の人たちというは、開発者以外に対して開発していないのに偉そうにするな、という見方をしてしまいがち」なので、諍いが起きないような関係が構築できればよいとまとめました。
溝部氏はまず「世の中のパブリッシングの難易度を並べると家庭用、次にアプリ、Steamの順」だと概観を語りました。その中でアプリが審査時間がかかるが一番簡単で、その次にSteamが簡単だと説明。審査が緩いのがいいが、ワールドワイドに向けて多言語対応をやろうとすると雑務が増えて面倒になるのがその理由だそうです。
溝部氏は「開発に集中したい方はパブリッシャーにお願いするのが一番」だと、ここまでの話をまとめます。ただ「あまり人に口出しされたくないとか、より独立心が高い方は自分でやったほうがいい」と、その付き合い方は人によることも示唆されました
一方、なる氏はSteamリリース後の問題について触れました。「Steamで特徴なのは、マウスとキーボード対応してないと炎上しやすい」らしく、さまざまなプレイヤーが使うインターフェースへ配慮していないと批判を浴びてしまうとのことです。
この批判は溝部氏もあったそうで、「コントローラー対応やってなくて炎上してしまい、マウス・キーボードと両方やらないといけない」と痛感したそう。司会の一條氏によれば、「ワールドワイドではキーボードを使うユーザーのほうが多い」といいます。
そこでhako 生活氏は「UI段階で、キーボードやコントローラー、そしてタッチパネルを全部同じ画面でプレイできるように対応できるようにした」と各インターフェースへ早い段階で配慮していたそうですが、最終的に仕上げる際、マウスとタッチパネルでは細かなインタラクションが異なっていたため、「あとで作業が地獄のようになってしまった」そうです。
またhako 生活氏がSteamで困ったこととして、「サントラもバンドルにして出したかったが、それができなかった」ことを挙げました。というのもSteamでのリリースは、リリース一週間前にストアページを公開してからじゃないと行えないシステムだからといいます。ゲームと同時にサントラ公開を行おうと思っても、サントラはゲームとストアページは別であるため、サントラはSteamの審査がかかってしまったそうです。(モデレータ 一條追記:Steamでのサントラ発売については次の記事が詳しいです:Steamworksの落とし穴まとめ ~Steamでゲームをパブリッシングしたいやつは全員読め~)
こうしたストアページを先に公開に関しては他の参加者もうなづくところであり、司会の一條氏も「マーケティングとしても、早めにストアページを出したほうがいい」とまとめていました。
また、hako 生活氏はSteamならではの炎上しかけたポイントに、実績システムについて触れました。
実績には表に内容や獲得の条件が公開されているタイプのほかに、秘密の実績という、内容や獲得条件が隠されたタイプがあります。『アンリアルライフ』では70個実績を作ったところ、遊んでいてもほとんど気づかないような場所に秘密な実績を仕込んだとのこと。
ところが「基本的に、実績をすべて埋めるつもりで遊ぶ」プレイヤーが想像よりも多かったそうで、理不尽すぎる実績を設定してしまうとユーザーからの反発に繋がりかけたそうです。
また、秘密の実績と言っても内容を知る手段があり、たとえばグローバル実績という、各プレイヤーの実績獲得率をまとめたページを参照すれば内容が確認できてしまう問題もあるそうで、hako 生活氏は「秘密の実績といっても、意外に事故になりやすい」要素があるとまとめました。
開発の大変さをどう乗り切るか?技術やチームのマネジメント、外注管理など
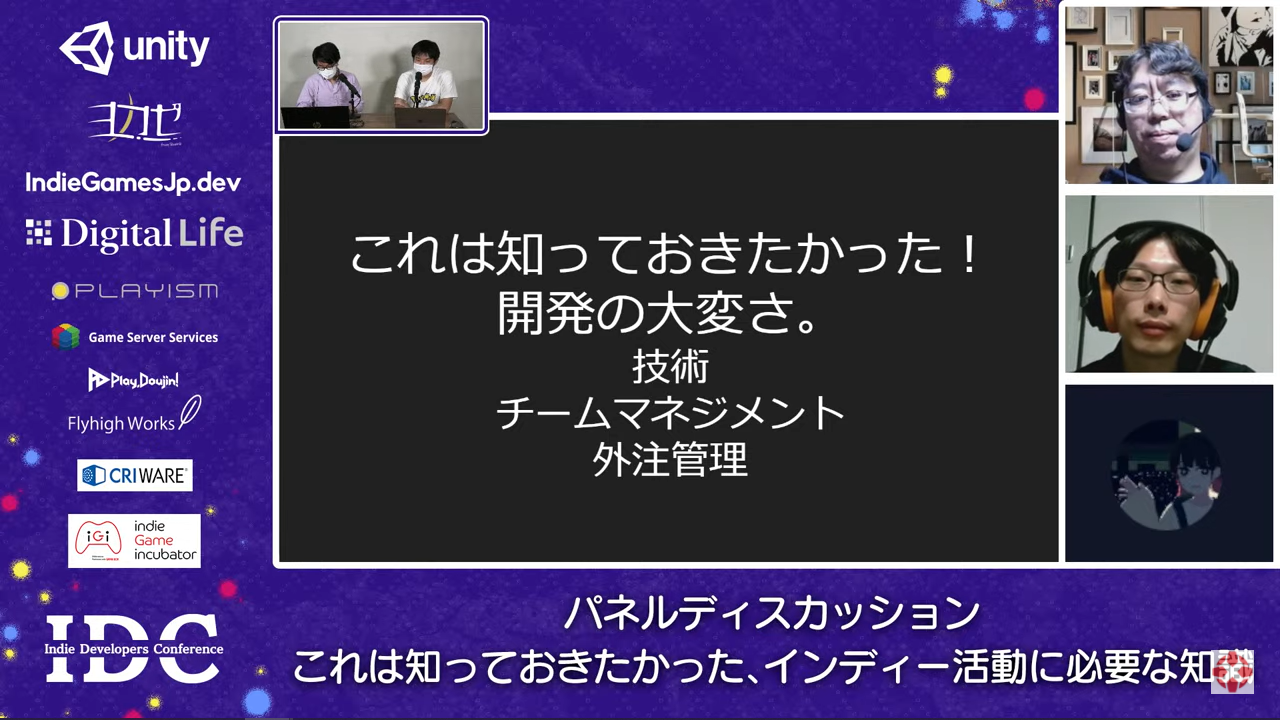
続いてトークテーマは、具体的なゲーム開発における問題について移りました。これはチームを組んでゲームを開発することや、開発における技術面のポイントなどについて参加者にうかがうものです。
川勝氏は開発のポイントとして、「やはりテストプレイやデバック」を上げました。これはパブリッシャーにお願いすることも多いそうで、「テストプレイ回数を重ねれば重ねるほど、ゲームの品質が上がるとメンバーは思い込んでる」といいます。
プチデポットでは4人のメンバーで片っ端からデバッグとテストプレイを繰り返し、その回数は「1000回から2000回」にも及んだといいます。
hako 生活氏も、川勝氏に同意する形でテストプレイはかなりやりこんでいたそう。『アンリアルライフ』は早くクリアしても4時間くらいかかるタイトルですが、1個でも直した時に、全体が機能しているかどうか確認するためにクリアまでテストプレイを行ったといいます。「ひとりで1週間かけてやっていた」と、念入りな様子がうかがえるでしょう。
川勝氏がその他に開発でこだわった点に「効果音や、ボタンを押した時のレスポンス気持ちよさ」を上げました。その理由として「ものすごくテストプレイすると粗が見えてくるため、ちょっとのレスポンスの悪さでもイライラしてくる」ためだそうです。なので先述の部分を細かくチューニングし、品質を向上させていったといいます。
話題は変わって、なる氏はチーミングにまつわる苦労を語ります。「人に逃げられるのがきつい」と、かなり切実な経験をふりかえってくれました。
「うちってメンバーが安定しない時期があって、人にお願いすると音信不通になる」ことが、これまでの開発経験でよくあることだったそう。これはお友達の感覚で作業をお願いしていったら、最初は早く仕上げてくれたが、次の作業は時間がかかり、その次の作業ははるかに遅れるようになり……と、だんだんとメンバーと疎遠になっていまった経験が語られました。
なる氏はそうした問題を回避するために「必ず契約書をかわせ」というのを自覚していたそうです。しかし、本人はそういうのは嫌いであまりやってこなかった模様です。ただ「お友達感覚でお願いすると、逃げられるのを前提としなければならない」のは確かなようで、「契約書をかわさないのは博打」であるとまとめました。
契約書をかわすというのは少し手間がかかる印象がありますが、司会の一條氏は「Webで公開されているIT委託系の契約書のテンプレートを活用して契約書を交わしている」とのことで、調べれば比較的、簡単にできるそうです。
川勝氏はチーミングにおいて「チームは崩壊することはよくある。繊細なもの」と指摘し、「小さいゲームでいいのでチームで完成させることが大事」と、チームで少しでも経験を積む重要さを語りました。
「何本か作ると、チームが合うかどうかわかる。チームが相性があるかわかる」ため、小さいプロジェクトでやりとりすることで、チームで開発する流れを掴んでいけるそうです。そこから規模の大きいゲームを作れるようにしていくプロセスを踏むことが大事だと説明しました。
技術的な問題に関して、溝部氏は『クラフトピア』開発において技術的な失敗をしたことを説明。「当初からパフォーマンスが悪くて問題になると思っていた」そうです。
開発にはUnityのDOTSというデータ指向型のテクノロジーを使用していたそうですが、これがあまりよい成果を得にくかったそう。「ゲームを作るのには技術は、枯れた無難なものを使うことがよい」と溝部氏は結論付けていました。
hako 生活氏は「(過去においては)Unityとドット絵のゲームの相性が悪かった」点を指摘。いまはUnityにもピクセルパーフェクトのカメラなどあるのですが、高解像度に対応したUIを組み合わせたりする際に非常に苦労したとのことです。
話題が開発のスケジュールに移ると、溝部氏は「ユーザーに告知するスケジュールが難しい」ことを挙げました。『クラフトピア』は当初、予定していたリリース日程をユーザーに告知したのですが、どうも開発の進捗から見て間に合わないことがわかったそう。
結局、延期する判断をしたのですが、これは「ユーザーからの信用が下がる」ため、やはり良くなかったと振り返りました。さらに延期すれば開発をゆっくり進められるかというとそうではなくて、「早く出さないと、信用を裏切ることになる」と追い立てられるようになってしまうとのことです。
hako 生活氏もリリース日程の告知と開発の進捗の遅れについて同意しており、「大作を初めて作るひとがリリース時期をいっても、スケジュールは1年遅れになる」ことを指摘。開発の進捗に関しても、「肌感覚では99%ができたら、そこから半年はかかる」と最終的な仕上げに時間がかかることを明言しました。
なる氏も「延期はよくやる」と同意。こうしたリリース日程と開発の進捗のジレンマについて、Play,Doujin!が提言していた「完成したら発表する」というのに賛同しているそうです。
お金の問題あれこれ。開発費や税金や控除、助成金について
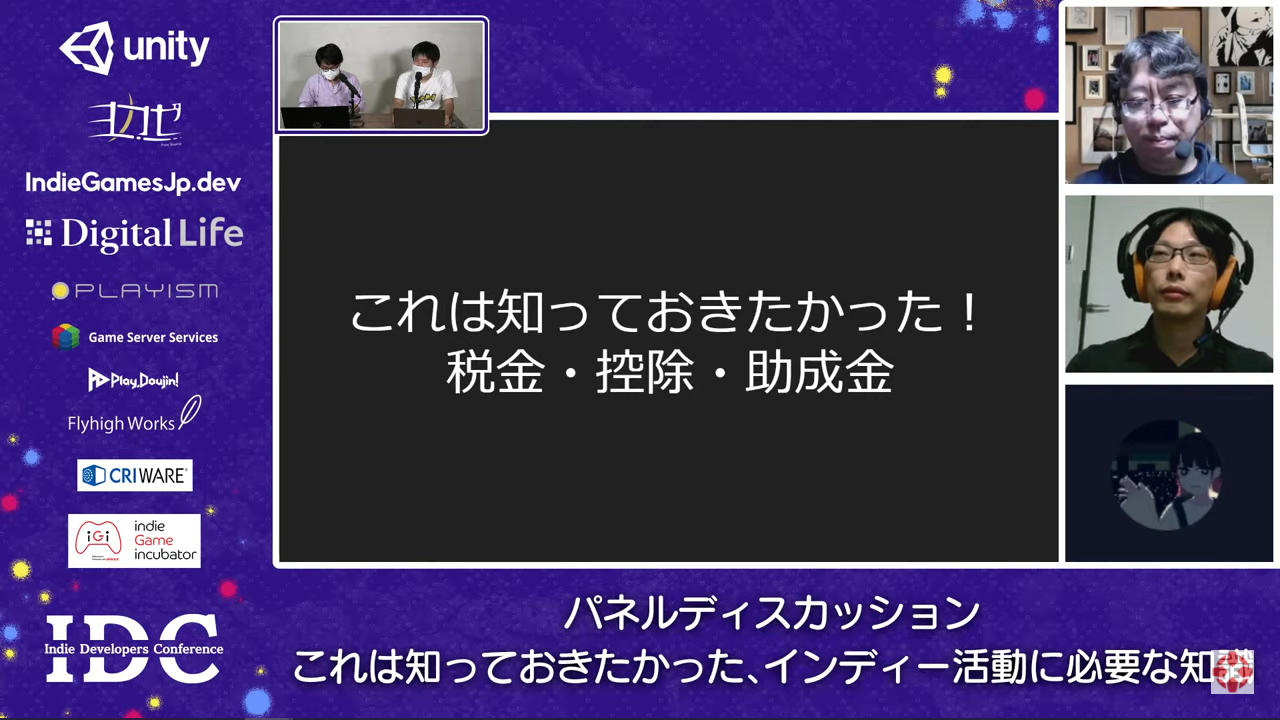
最後のトークテーマには税金や助成金の問題が取り上げられました。ゲーム販売の収益はどうするのか、開発を続けるための助成金とはどのように付き合うのかについて語られました。
溝部氏はゲームの収益について「思ったより残らない」と語りました。『クラフトピア』の販売価格は日本では2570円ですが、実際には地域ごとに販売価格が違うそうです。さらにSteamの手数料として、収益から3割が引かれ、そこからさらに各国の消費税の控除が加わると、収益はかなり取られてしまう。そこから入金しても、今度は法人税が引かれるため、収益は想像以上に残らないのだと説明しました。
川勝氏はインディーゲームにおける開発費について触れました。大企業開発によるゲームとは違い、開発費=メンバーの生活費というくらいの規模であると前置きし、「1カ月の生活費をいかに押さえるか」がわかりやすい開発費の捻出となるとのこと。
川勝氏は名古屋に住んでおり、「土地の物価が高くないわけではなく、質素な生活をしている」ことで生活費……いや開発費を押さえているそうです。基本的には貯金通帳を切り崩していく形になる「これがダメでも他の仕事をやればいいんだ」という気持ちでやってないと大変とのことでした。
しかし、こうした開発のスタイルには困難も。hako 生活氏も同じく「最初は自分も貯金切り崩しだった」そうですが、お金が無くなってくると身体が動かなくなっていくという精神的な問題もあったそうです。困ったとき、room6からお仕事を貰う形でなんとか凌いだそうで、開発費=生活費の捻出において「プランB、プランCというかたちで2、3案を考えていた」そうです。
なる氏は『天穂のサクナヒメ』を作って、一時期は貯金が0まで行ったことも。ほとんどお金を考えずに作っていたとのことです。
話題が助成金についてに移ると、意外にこれが簡単な助けになるかというとそうではないことが語られました。たとえばパブリッシャーからの助成金を受け取ることができるのですが、「お金が絡んでくると関係を切りにくくなる」という問題が生まれることもあるそうです。
最後に話題は「ゲームの販売価格をどうしているのか?」についてトークが行われました。川勝氏は「みんなどう考えているのか?」と疑問を持っているようで、解答には各クリエイターのスタンスが出たものとなりました。
hako 生活氏は「安くたくさん買ってもらうより、高くしたほうがレビューの質が上がると思った」と説明し、『アンリアルライフ』ではインディーのADVとしては比較的、高めに設定していました。個人の作家性を推したタイトルゆえに、こだわった面もうかがえます。
対して溝部氏は「競合タイトルの水準に合わせる」かたちで決定したとのこと。『クラフトピア』は同じクラフト系ゲームの価格帯に合わせた値段となっており、広いプレイヤーに触れてもらうことを考えた戦略どおりだと言えるでしょう。
一方、なる氏は「どう値段をつけても高い、安いという人が出てくる」と価格設定の難しさを語りました。「双方に理解がある範囲で、可能な限り、勇気を出した高めにつける」と結論付けています。
一條氏はこうした開発費から税金周りのまとめとして、「お金周りの知識があると、将来的な危機を回避できる」と語りました。インディークリエイターは開発だけではなく、さまざまな雑務も自分でこなさなくてはならないシーンが多いため、今回のパネルディスカッションではどのようにそうした課題をクリアしたかのヒントがまとまっていたといえるでしょう。








