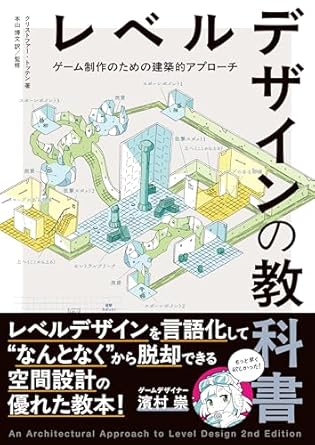インディーゲーム開発者のためのVRゲーム入門ガイド(3):そもそもインディーゲームってどう宣伝するの?

IndieGamesJp.dev編集部より:
今回から新たな試みとして、さまざまな有識者に寄稿を依頼し、個人・小規模ゲーム開発に役立つ情報を発信する連来シリーズをスタートします。開発者、パブリッシャー、弁護士などから、ゲームを開発・配信するために必要なノウハウをご紹介します。
第一弾として、「VRゲームのいま」というテーマで渋谷 宣亮氏に寄稿いただきました。書籍『「VRならでは」の体験を作る Unity+VRゲーム開発ガイド』を執筆し、MyDearest株式会社で『クローバークライマー』などを開発しています。
連載の前回はこちらです。
●まえがき
日本発のVR専用ゲームとして一番売れているのはおそらくVRカノジョなのですが、Meta Quest上でほぼ個人開発レベルの買い切りVRゲームを20万本以上販売された経験がある日本のゲーム開発者は、おそらく筆者しかいないのではないかと思います。
正確には私が自分自身でCrowbar Climberを広報、宣伝を担当したわけではありませんが、Crowbar Climerが売れる様子を見てきました。VRゲームがどのように売れていったのかを日本語で言語化する機会は、このケース以外に存在しないでしょう。
個別のケースに依存するものであるとか、機密事項に抵触するようなことは言及できません。しかし、あくまで一般に公開されたデータの範疇でありつつ、あらためて言語化をすることに意義はあるはずです。
それと、筆者がCEDEC 2025で講演したスライドを公開しております(Google Slide, CEDiL)。今回の記事の内容と関連している箇所も多いので、副読本としてぜひご一読ください。
なお、以下のふたつがございます。あらかじめご了承ください。
(1)本記事で触れられている情報はすべてSteamやMeta、Redditなど開かれたプラットフォームの公式ドキュメント、データベースで得られる情報をもとに記載されており、機密情報は一切含まれておりません。また、CEDECで発表した情報はCEDECのアーカイブ”CEDiL”でにすべて記録、公開されているものです。
(2)宣伝についてはインディーゲーム市場における基本的な戦略と筆者の経験則および独自研究に基づいているもので、筆者が業務の一環として得た情報は一切含まれません。筆者はCrowbar Climberのマーケティング業務に関与していません。
●インディーゲームの宣伝戦略
まず、VRを抜きにして「インディーゲームの宣伝戦略」について考えてみましょう。パブリッシャーに委託しなかったり企業で販売してない日本のインディーゲーム開発者の場合は、おおよそ以下の事項のいくつか、またはすべてを実施すると思います。
・TwitterほかSNSでの宣伝、拡散
・YouTubeへのトレイラー作成、動画投稿
・ゲームメディアへのプレスリリース送付
・個人でのSteamストアページ作成
・インディーゲームのパブリッシャーへの持ち込み
・Discordサーバーの運営
しかし、VRゲームの宣伝を通して筆者が学んだのは、日本人のインディーゲーム開発および広報活動は「日本のゲーム市場のエコシステム」に大きく依存した形であるということでした。
前提として、日本という地域は自分たちの言語圏だけでビデオゲーム市場としての規模感があり、長い歴史の中で紙・Webメディアやインフルエンサー、ファンコミュニティといった強靭な生態系が形成されています。このため、自分たちと同じ言語圏で同じようなプラットフォームを利用している、それなりに厚いユーザー層に宣伝をしかけることができます。開発者とユーザーの価値観とライフスタイルがもとから近いわけですね。
一方、グローバル市場(特にVR分野)では、ユーザーが用いる言語や普段使うSNS・サービスが非常に多岐にわたり、まとまったコミュニティが日本ほど確立されていない場合もあります。パブリッシャーもいない市場に対してアプローチしなくてはならないとしたら、どうでしょうか?こういうことを考えるのが好きな人は、VRゲームの市場に向いています。
結果として、Crowbar Climberの宣伝活動として実施したのは以下の施策となります。それぞれ詳細を書きます。
・Redditほか海外SNSでの宣伝、拡散
・YouTubeへのトレイラー作成、ショート動画投稿
・ゲームメディアへのプレスリリース送付
・個人でのSteamストアページ作成
・Discordサーバーの運営
●SNS運用: 薄く広く、ときおり深く。DMも要確認。
この章のポイントは以下の3つです。
・SNSの運用は複数かけもちしたほうがよい
・DMやメッセージは常に確認すべし
・作法に合わせよう。しかし無理は禁物
前提として、宣伝はターゲットユーザーが見ている場所でやるのが効果的です。洗剤や掃除器具といった生活必需品、消耗品であればゲームメディアの広告バナーではなく地上波のTVCMが適切であるように、それぞれ適材適所があります。SNSも同様に、どういったSNSにどんなユーザーがいるのか傾向があるわけです。
日本のビデオゲーム市場においては、日本人のゲーマーはX(旧Twitter)ユーザーが多いとされているので「いかにX(旧Twitter)を制すか」といったことが考えられがちですが、X(旧Twitter)でVRゲームを宣伝しても反応が少ないと常日頃に思っています。MetaプラットフォームでヒットしているVRゲームのタイトルで検索しても、日本語はおろか英語でもポスト(旧ツイート)の検索結果にほとんど出てこないからです。
常日頃からVRゲームをプレイしている人がX(旧Twitter)というSNSで情報を発信しているのかというと、おそらく違うのです。とはいえ、X(旧Twitter)は、VRゲームはおバカ系のプレイ動画やその転載ショート動画が流行りやすい傾向にはありますし、ユーザーよりも開発者ないし業界人が多く滞在しています。また、筆者の知り合いの英語圏のVRゲーム開発者には、主なファン層がInstagramとX(旧Twitter)にいるとのことがあります。何ごとにも例外はあります。
世の中は広いわけですから、X(旧Twitter)以外のSNSもいろいろ試してみるとよいです。FacebookとかInstagramとかRedditとかTikTokとかYouTubeとか、いろいろあります。動画投稿も欠かせません。
そして、なにより重要なのは各種SNSにアカウントを作っておくことで何かしら重要な連絡がDMに来る確率がぐっと高まることです。むしろ宣伝より重要です。
なんらかインフルエンサーを名乗る人物から「あなたのゲームに興味があるから、ストアのキー(ゲームの購入権利)を無料でくれ」とDMが来るかもしれません。場合によっては「それぐらい自分で買えよ」とか「安売りはしない主義です」といってDMを見なかったことにすることもありますが、この連絡を受けてキーを無料で一本相手に渡したことによって数千倍から数万倍のリターンになって返ってくることも、ないわけではありません。とはいえ、すべてのDMでミラクルが起きるはずもないので、相手の素性はさっくりと調べてから返答すべきでしょう。
●動画作り:重要なのは”自分のゲームを理解しているか”。
インターネットでどこでも動画が見られる現代においては動画がもっとも強力なツールなのは間違いありません。しかし、動画にしろなんにしろ、本質的な問題は「自分が作ったゲームの魅力を自分自身が理解しているか?」です。これが理解できていなければ、どんなにイケてる演出を入れてもどうしようもありませんし、理解していれば、どんな尺だろうが効果的な動画作りができます。
ゲームの宣伝において重要なのは「これはどういったゲームなのか」と「このゲームをプレイすることでどんな体験ができるか、気持ちになるか」のふたつです(コンセプトとかログラインいろいろ言い方があります)。筆者が作った『Crowbar Climber』であれば「両手に持った2本のバールで崖を登るVRのアスレチックゲーム」というゲームプレイと「崖から滑落しそうになって怖がったり焦ったり必死になったりしている人を見るのは面白い」という気持ちが伝わればよいわけです。あとは、録画したゲームのプレイ映像から該当箇所を切り貼りすれば、トレイラーだろうがショート動画だろうが、視聴者に意図が伝わる映像はできます。
また、VRゲームならではの映像の特徴として「主観視点であること」と「プレイヤーの身体表現がダイレクトに反映されること」があります。これはふつうの映像にはない(一般的な一人称視点のゲームを大きく上回る)臨場感や生っぽさが出やすい一方、客観的には何が起きているのか分かりにくくなる副作用も生じます。
この問題へのひとつの策として、主観視点ではない映像を混ぜるというものがあります。これは実際にCrowbar Climberでも導入しており、筆者の狙いとしては「主観視点の躍動感と臨場感のある画角」と「プレイヤーを客観的に映すスポーツ番組のような画角」を交互に流すことで、ゲームの魅力を伝えやすくしました。これはCrowbar Climberにおいてはうまくいきましたが、そもそもVRゲームではプレイヤーの客体の姿を映すのが仕様上できないことがあるとか、客体で撮影してみたけどいまひとつだったとか、「客体を映す」は必ずしも万能の策ではありません。自撮り風のアングルや監視カメラ風の映像とかいろいろ試行錯誤の余地もあるかとは思いますが、まずは一人称視点で面白そうに見えることに注力して、その先は後から考えましょう。なにより、VRはまず主観視点の躍動感が共感を生むわけですから。
筆者オススメのVRゲームのトレイラーとしては、長尺のトレイラーとしては『Boneworks(2019)』のリリースデートトレイラーが最高傑作です。6分半にわたって本編のゲームプレイの映像を流しているだけなのですが、ゲームシステムのリアリズムや展開に引き込まれる迫力があります。
短い尺のトレイラーとしては、『Project Mix(リリース時期未定)』が衝撃的です。たった30秒のゲームプレイの切り抜きの映像だけで、本作がどういったユーザーに向けられたVRゲームなのか、どういった体験が待っているのかを完璧に伝えきっています。VRはこうした、世間一般的なカット割りや映像の構成といった作法を越えた場所にある一点のパワーだけですべてを超越してしまうマジックリアリズムが宿ることもあります。
余談ですが、よくもわるくもゲーム開発者は自分が作ったゲームがどんな意図で作られたかを知っているわけですから、いざ自分でゲームをプレイしようとすると自分の理想のゲームプレイを演じてしまう癖があります。こういったプレイ映像はだいたい予定調和で見ていて面白くないものになりがちなので、知り合いや友人などにゲームをテストプレイしてもらって、それを録画してよい箇所を切り出すのも手段のひとつとしてアリでしょう(その場合は動画に使う旨の同意を取ることを忘れずに)。
●Reddit:宣伝の穴場。インターネット掲示板に飛び込め!
Redditは世界でもっとも普及しているインターネット掲示板です。日本のゲームメディアもよくRedditで注目の話題を記事化するなどなにかと話題を追いかけるには便利な場所であり、世界中のゲーム開発者がRedditに自身のゲームを宣伝しています。
ひと昔前では、Redditのことを「英語圏の2ちゃんねる」だとよく説明されましたが、ゲーマーのコミュニティがX(旧Twitter)に集中した現代日本においては2ちゃんねるそのものが伝わらないこともあります(Redditは本来2ちゃんねるではなくふたばちゃんねるのフォロワーですが、そういった話の前提となる文脈が現代は失われています)。
たとえば、X(旧Twitter)やFacebookのようなSNSでは主体的にしろ受動的にしろ、なにかしら利用者ごとにパーソナライズされた情報が流れてきます。一方、インターネット掲示板ではジャンル別の掲示板があり、何かしら話題を取り上げたい利用者が話題を投稿します。この投稿に対して不特定多数の人々が話題に対して各々の書き込みを連ねることによって、スレッドが成立します。
X(旧Twitter)では情報の主役はあくまで主となる”ポスト”(旧ツイート)であってリプライは副次的なものですが、インターネット掲示板では起点となる投稿に対して不特定多数のユーザーが投稿を重ねて”連なり”(スレッド)を作ることで、価値が生み出されていく、といった違いがあります。
先述のように、日本におけるインターネット掲示板の代表格だった2ちゃんねる(および、5ちゃんねる)は現代のゲーム情報のメインストリームというにはやや存在感が薄く、アングラ感が強いために”公式(オフィシャル)”が存在感を出すことがはばかられる場でもあります。一方、Redditは(アングラ感がないわけではありませんが)企業公式や宣伝目的で何かしら投稿したり利用したりできます。
ただし、Redditには”Subreddit”と呼ばれる概念があり、要はジャンル別の掲示板ごとに管理者が異なり、それぞれ独自のルールが設けられています。インターネットにおけるルールの大半は「他人に迷惑をかけてはいけない」に要約されますが、たとえば「これまで何の書き込みもしていない状態から、いきなり話題を投稿してはいけない」とか「一日に投稿してよい数はXXまで」とか、いろいろありますので、投稿する前はよく読んでから投稿しましょう。
なお、筆者はUnity、インディゲーム、VRの三つのSubredditに投稿した結果、ビュー数はVR、Unity、インディゲームの順でした(社内インディー攻略法! VRゲームが中ヒットに いたるまでの道のり, P34より)。

●パブリッシング:SteamとMetaの主なちがい
ゲームのパブリッシングに伴う作業というのは、どこであろうと大差はありません。ゲームのビルドを提出し、ストアに並べるために必要な情報を入力、ストアで商品を魅せるための画像、スクリーンショット、映像を用意します。このあたりは、Steamでの提出の仕方を解説している記事などを見ればおおざっぱにつかめることでしょう。
しかし、MetaはSteamではありませんし、独特の癖や違いがあります。それはストア側の仕様もそうですし、ユーザー動向やデバイスによる利用形態の差もあります。
(1)ストアへの製品登録料は無料
Steamは新しいゲームを開発者アカウントに登録するごとに申請料金が100ドル(2025年時点で1万5000円前後)を支払う必要がありますが、Metaはいくら申請しても無料です。「無料で登録できるということは、スパムのようなゲームが山ほど出品されているのではないか」と心配されるかもしれません。これは実際にその通りなのですが、登録に100ドルが要求されるSteamであったとしてもほぼほぼスパムのようなゲームが山のように出品されているのは変わらないので、五十歩百歩の差だとは思います。
(2)オフラインゲームでもプライバシーポリシーが必須
Metaのストアで地味に不便なのがプライバシーポリシーの登録です。Steamにおいてはオフライン(インターネット接続およびユーザーのデータ収集が不要)のゲームであればプライバシーポリシーの登録は不要なのですが、Metaでは仮にオフラインゲームであってもプライバシーポリシーの登録が必要となります。書き方については、適宜必要な法律の情報を調べるか、自身の作るVRゲームと類似している既存タイトルがどのような書き方を参考にするとよいでしょう。とはいえ、審査もピンからキリまであるのか、一般的にプライバシーポリシーは自社ホームページなどに記載するのが一般的ですが、Google Documentにプライバシーポリシーを記載してそれをURL共有するだけでも審査が通ることもあるようです。
(3)検索性がいちじるしく低い
MetaストアはSteamと比べて検索性がかなり低いのですが、これには二つの意味があります。一つ目が、本当の意味でストア自体の検索性が低いのです。なにかというと、以下のツイートのように「部分一致」がまったく信用なりません。Metaもこの問題を意識してはいて改善の意図はあるようですが、とりあえず今はびっくりするほど検索性が低いです。Steamのようにプラットフォームとしてのコミュニティ機能が使われておらずユーザーが書きこめるフォーラムもないので、”内部コミュニティから湧き上がる”ようなことも起こりづらいです。
また、もう一つの検索性の低さは「VRデバイス」ゆえに生じます。Metaが開発者向けのブログで「ユーザーの半分以上がVRヘッドセットからVRゲームを購入する」と解説しています。一見普通のことを言っているように聞こえますが、VRヘッドセットをかぶっているときに使う”バーチャルキーボード”ってすごい使いづらいんです(例えるならレーザーポインターで1本指打法をするような感じです)。つまり、ユーザーがスマートフォンやPCほどスムーズに文字入力ができない状況で文字検索をしないといけないわけですから、Metaも「あんまり入力しづらかったり覚えづらかったりするようなタイトルをつけると、検索で見つけてもらえないよ」と警告しています。そういった意味では、”Crowbar”と”Climber”の組み合わせは英語ネイティブにはシンプルで覚えやすい名前だったはずです(ただし日本人にはClimberのスペルが難しいのでは?とよく言われました)。
(4)ユーザー層がかなり違う
以下の画像は、CEDECの講演で筆者が公開した情報です(このデータの公開については、株式会社MyDearestから許諾がおりています)。ざっくり述べると、Crowbar ClimberのMeta Quest売上のおよそ8割が北米および英語圏で占められる一方、Steamは英語圏が多数派であれど国籍の比率は多種多様であったというものです。また、。このデータは「あくまでCrowbar Climberがそうだった」という話ですが、言語依存性や文化依存性の低い(地域や文化によって好き嫌いが分かれない)VRゲームを販売するとなると、Crowbar Climberとあまり変わらない比率になるのではないかと筆者は考えています(社内インディー攻略法! VRゲームが中ヒットに いたるまでの道のり, P36より)。

とはいえ、「VRゲームの売り上げはほとんど北米で占められ、プラットフォームはMetaが大半である」という結果に飛びつくわけにもいきません。なぜなら、Crowbar Climberの結果が「言語依存性がなく」「文化による嗜好差が生じない」ことによるものならば、言語依存性があったり、文化によって嗜好差が生じるVRゲームならば、結果もまた異なるからです。ストレートにいえば、日本語しか対応していないとか、ゲームの嗜好がすごく日本っぽいものならば、ターゲット層は自然と日本っぽいモノを好きな人々になります。
また、言語や文化だけでなく、ハードウェアによる差も生じます。たとえば、ゲーミングPCとMeta Questでは天と地ほどのスペックに差があり、PCの処理能力のリッチさに依存したソフトウェアは移植しようがありません(あるいは、モバイル相応にダウングレードするか)。
わかりやすいのは、SteamVRやPSVR2だと車を題材にしたVRゲームは人気がありますが、Meta Questではさっぱり人気がありません。これはMeta Questの描画能力だと車の見た目がPCと比べて格段にへぼくなってしまうこと(レースゲームは昔からCG技術のショーケースと言われるほど、見た目が重要なジャンルです)、PCやPSVR2だとゲームパッドやハンドルコントローラーで車を操作することが没入につながるのに対して、Meta Questのモーションコントローラーについているスティックやトリガーによる操作は車の操作に適しているとはいえないというのがあります。
逆に、Meta Questはケーブルレスなのでダイナミックに動いたりカジュアルにインスタントに遊べるものが好まれる傾向にありますが、デスクトップPCを前提にしてVRゲームを遊ぶとなると、(PCとVRデバイスを無線接続していたとしても)ダイナミックに動くものよりも、落ち着いて濃厚に没入するとか、カジュアルさやインスタンスさみたいなものはあまり求められていない傾向にもあります。
もし「自分の作っているVRゲームはどちらに向いているのだろう?」と思った場合、特にハードウェアやプラットフォーム依存の機能を重点に置いていない限りは、どちらでも同時にリリースすることをオススメします。ゲームによって客層やプラットフォームに向き不向きはありますが、自分が思っていなかった箇所への適性を見つけられることがありますし、なにより重要なのは「自分が戦うべき場所はここだけだ」という思い込みを壊すことです。VRではないインディーゲームにしたって、戦うべき場所はSteamだけではないはずです。
●だいじなこと:努力は大事だが、すべてを制御できると思わないこと(精神衛生によくないため)
近年ではSteamは年に1万本以上のゲームがリリースされるのは当然といった状況であり、この世には山のようにゲームがあふれています。MetaやVRゲームも同様に、狭いプラットフォーラムや世界といえども、それでも新作なりベストセラーなり競合はそれなりにいるわけです。ゲームのプラットフォームだけでなく、SNSも同様です。マネーゲームに持ち込める資本のある企業ならともかく、やはり個人単位で情報を発信して、すべてがバズになるなんてことはそうそう起きません(起きたら、全力で喜びましょう)。
インディーゲームにおける個人規模のマーケティングで重要なのは、なによりも自分の作っているゲームの品質をあげ、自分自身が作っているインディーゲームの魅力をより考察して理解を深めることです。これを自覚的に行えるようになれば、「自分の作っているインディーゲームは誰に届けるべきで、そのためにはどんな手段を用いればいいのか」ということがわかるようになってきます。それに「面白い」に勝るゲームの評判は、この世界にありません。
これができていたら、あとはチャンスが巡ってきたときに逃さないことです。人間においてもっとも普遍的なマーケティングツールは口コミであり、たいていは開発者自身ではない他人が火をつけるものです。その火がついた瞬間を見逃さないようにし、火をより大きくする努力(火をつけた人と連絡をとるとか、ゲームをアップデートするとか、何かしらの告知をするとか)をしましょう。一発目はダメでも、二発目、三発目の火が付いたときにこういった努力を継続すれば、自然と火は燃え広がるものです。なによりも諦めないことが肝心です。
(インディーゲーム開発者のためのVRゲーム入門ガイド(4)へ続く。)